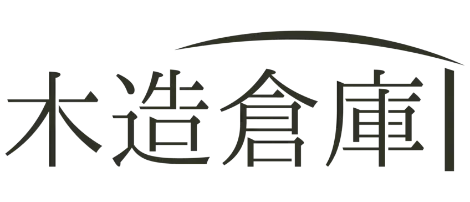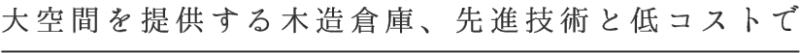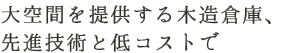昨今は環境配慮のテーマが話題となっており、「脱炭素」といった言葉を見たり、聞いたりしたことがある人も多いでしょう。実は木造倉庫は脱炭素社会に大きく貢献しており、木造倉庫を建てることで企業アピールにもつながるのです。
そこで、今回は脱炭素とは一体どういったものなのか、そして脱炭素が重要視されている理由に加え、脱炭素と木造倉庫の関係について見ていきましょう。
脱炭素とは?

地球の気温が上昇し続けると、異常気象が増えたり、生態系が変化したり、人々の暮らしに大きな影響を及ぼします。主な原因は、石炭や石油、天然ガスといった化石燃料を燃やすことで発生するCO₂(二酸化炭素)です。
二酸化炭素の排出量を減らすために、日本のみならず世界各国が「脱炭素」に向けた対策を進めています。
脱炭素の方法はいくつかあります。たとえば、電気をつくるときにCO₂を出さない「再生可能エネルギー」の活用が挙げられます。太陽光や風力、水力発電などはその代表例といえるでしょう。
太陽光や風といった自然エネルギーを活用して電気をつくれば、化石燃料を使用せずに済むので、結果的に二酸化炭素の排出量を抑えられるのです。
また、ガソリン車を電気自動車に切り替えたり、省エネを進めたりすることも効果的です。さらに、二酸化炭素を吸収すると言われている森林を増やすことも、重要な取り組みのひとつといえるでしょう。
脱炭素が重要視されている理由

脱炭素がどういったものかを理解できたものの、そもそも脱炭素が重要視されている理由がいまいちわからない人も多いでしょう。二酸化炭素の排出量が増えることで、どういったトラブルが起きるのでしょうか。
地球温暖化の防止のため
二酸化炭素の排出量が増えると地球温暖化が進むと言われています。二酸化炭素の排出量が増えると地球温暖化が進むのは、二酸化炭素が「温室効果ガス」としての役割を果たすからです。
地球は太陽からの光を受け、そのエネルギーの一部を地表に吸収します。吸収された熱は、地表から宇宙に向かって放出されますが、大気中の二酸化炭素などの温室効果ガスがこの熱を吸収してしまい、一部を地球に戻します。これにより、地球の表面は適度な温度に保たれ、生き物が暮らせる環境になっています。
しかし、化石燃料を大量に燃やすと、二酸化炭素濃度が高くなり、熱を閉じ込める力が強まります。その結果、本来なら宇宙へ逃げるはずの熱が地球にとどまり、地球上の気温が上昇してしまうのです。
気温が上がると、異常気象が増えたり、海面が上昇したりするなど、さまざまな影響が出ます。たとえば、氷河が溶けて海水の量が増えると、沿岸地域が水没するリスクが高まります。また、気温の変化によって生態系が乱れ、動植物が絶滅の危機にさらされることもあるのです。
木造と鉄骨造の二酸化炭素排出量の比較

建物を建てるとき、木造と鉄骨造では二酸化炭素の排出量に大きな違いがあります。木造のほうが環境に優しいとされる理由は、主に2つのポイントが考えられるでしょう。
まず、材料を作る過程での二酸化炭素の排出量の差です。鉄骨造の主材料である鉄は、鉄鉱石を高温で溶かして精錬する必要があります。この工程では大量のエネルギーを使い、その結果として二酸化炭素が多く排出されます。
一方、木造に使われる木材は、伐採や加工の際に必要なエネルギーが比較的少なく、二酸化炭素の排出量も抑えられます。
次に、木材の二酸化炭素の吸収・固定の特性です。木は成長する過程で二酸化炭素を吸収し、内部に炭素として蓄えます。木造の建物に使用された木材は炭素を固定し続けるため、大気中の二酸化炭素削減に貢献します。
一方、鉄骨造にはこうした性質がなく、建設時に排出した二酸化炭素がそのまま環境に影響を与えます。
こうした違いにより、同じ規模の建物を建てる場合、木造のほうが鉄骨造よりも二酸化炭素排出量を大幅に抑えられるとされています。そのため、脱炭素社会を目指す中で、木造建築の活用が注目されているのです。
木造建築と鉄骨造建築の二酸化炭素排出量の違い
ここでは、具体的に木造建築と鉄骨造建築の二酸化炭素排出量の違いを見ていきましょう。
※日本建築学会:建物のLCA指針第3版(2006)、データベース表2,3,2(国内消費+資本形成分のみ)より
上のグラフのように、木造、鉄骨造、RC造を比べてみると、二酸化炭素排出量の違いがわかるでしょう。同じ規模の建物を作る場合であっても、木造と鉄骨造とでは、約1.5倍の差が生じるのです。
木造倉庫がSDGsに貢献できる理由
木造倉庫は、SDGsの達成に貢献する建築のひとつです。環境への負荷を抑えながら、資源の持続的な利用や、人々の暮らしの質の向上に寄与する特徴を持っています。
まず、先述の通り、木材は成長過程で二酸化炭素を吸収し、炭素を内部に固定する性質があります。そのため、木造倉庫を建てること自体が、大気中の二酸化炭素を削減する役割を果たすのです。一方、鉄やコンクリートを使った建築物は、製造時に大量のCO₂を排出します。したがって、木材の活用は脱炭素に貢献する有効な手段となります。
さらに、木材は再生可能な資源であり、適切な管理のもとで植林と伐採を繰り返せば、持続的に利用することができます。これはSDGsの目標「陸の豊かさを守ろう(目標15)」にもつながる取り組みです。
木造倉庫は断熱性が高く、夏は涼しく冬は暖かい環境を保ちやすいため、空調管理に必要なエネルギーの使用を抑えるのも特徴のひとつです。倉庫の運営におけるエネルギー消費を削減し、二酸化炭素排出量の抑制にもつながります。これは、「エネルギーをみんなに そしてクリーンに(目標7)」や「気候変動に具体的な対策を(目標13)」といった目標にもマッチするといえるでしょう。
また、木造倉庫は働く人の健康や快適性にもいい影響を与えます。木には湿度を調整する性質があり、快適な空間をつくりやすいため、作業環境の向上にも寄与します。これは「働きがいも経済成長も(目標8)」につながるポイントです。
このように、木造倉庫はCO₂の削減、資源の持続可能な活用、省エネルギー化、そして働く人の快適性向上など、さまざまな面でSDGsの目標と深く関わっています。環境と経済のバランスを考えた建築として、今後ますます注目されるでしょう。
木造倉庫なら企業アピールができる

木造倉庫なら企業アピールに貢献することが可能です。
昨今は日本のみならず、世界中で環境への配慮が話題となっています。環境に配慮した会社経営は対外的なアピールとなり、企業評価を高められるでしょう。
これから、倉庫の建築を検討するにあたり、木造倉庫か鉄骨造倉庫、どちらにしようか悩む人も多いでしょう。木造倉庫であれば環境に配慮していることを対外的にアピールできます。
さらに、鉄骨造倉庫よりも少ない予算で建てられるのも木造倉庫の魅力といえます。愛知県で木造倉庫の建築を得意としているHC Home’sであれば、1坪あたり25万円から木造倉庫の建築が可能です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は「脱炭素」をテーマに、木造倉庫と脱炭素の関係性や脱炭素の重要性について解説しました。木造倉庫で使用される木材は、二酸化炭素を吸収して炭素を固定かさせる性質があり、脱炭素社会に大きく寄与します。
その結果、木造倉庫を所有している企業は、対外的なアピールができて企業評価を高められるでしょう。さらに、鉄骨造倉庫よりもリーズナブルな価格で建てられるのも木造倉庫の特徴です。
愛知県で木造倉庫の建築を検討している方は、ぜひHC Home’sにお任せください。