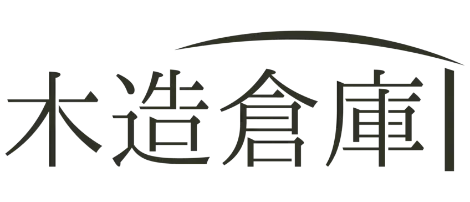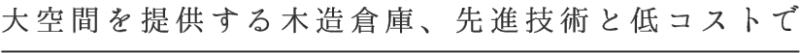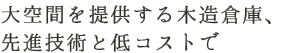物品を大切に保管するための倉庫には、「営業倉庫」と「自家用倉庫」があります。商業用として倉庫を活用するためには、それぞれの目的や特徴、倉庫運用にかかわる倉庫業について把握する必要があります。
そこで、今回は、営業倉庫の特徴や自家用倉庫との違いに加え、倉庫業の概要と倉庫業法について解説します。ぜひ、参考にしてください。
営業倉庫とは?

営業倉庫とは、第三者の物品を有料で保管する倉庫のことを指します。営業倉庫は、倉庫業法に基づいて、防火・防水対策など適切な基準をクリアして国土交通大臣より登録を受ける必要があります。
国土交通大臣による登録を受けないまま、営業倉庫の運営をおこなうと、罰則や罰金が課せられてしまいます。また、未登録の状態で火災などの事故が発生した場合は、保険が使えないケースがあるので気をつけましょう。
営業倉庫の建設の際は上記の倉庫業法の基準のほか、建築基準法や都市計画法などの一般的な建設基準も満たす必要があります。
営業倉庫はおもに物流会社や倉庫業者によって運営されており、多くの企業がこの営業倉庫を保管スペースとして利用しています。企業は自社で倉庫を持たずに済むため、コスト削減や物流の運営効率化が期待できる運営方法です。
自家用倉庫とは何が違う?
自家用倉庫は、個人や法人が、自身の所有物や商品・原材料を保管するための倉庫を指します。他者の物品を取り扱わない点が営業倉庫との大きな違いになります。
営業倉庫では製造した商品を企業から預かりますが、自家用倉庫では製造した商品をそのまま自社で保管します。個人が自身の荷物をしまうために敷地内に建てた倉庫も、自家用倉庫です。
企業自身の敷地内に自家用倉庫を設置するため、流通コスト削減でき、体制を整えられるというメリットがあります。
自家用倉庫を建設するには、倉庫業法は関係ありませんが、建築基準法や都市計画法などの一般的な建設基準を満たす必要があるので注意しましょう。
倉庫業とは?

倉庫業は、おもに営業倉庫を運営し、物品の保管を提供する事業です。倉庫業の役割は単なる保管にとどまらず、在庫管理、流通加工、ピッキングなど、流通全体を支える役割を担っています。
また、保管中の物品の品質や数量を適切に維持する義務が課されており、厳格な管理体制が必要となっています。
そのため、倉庫業を営むには倉庫業法に基づき倉庫の目的に合った建設基準を満たした営業倉庫の設置が義務付けられおり、倉庫の管理を適切におこなうために倉庫管理主任者の選任も必要です。
なお、ひとえに倉庫業といっても事業の内容によりさまざまな種類にわけられます。その中でも代表的な倉庫業を見ていきましょう。
・普通倉庫業
普通倉庫業は、おもに一般的な物品を保管する倉庫を運営する事業です。食品、衣類、雑貨、建材など、特別な温度や湿度管理が不要な物品を安全に保管します。普通倉庫業の倉庫では、基本的に屋内で保管をおこない、物品の入出庫管理や在庫管理をします。
・冷蔵倉庫業
冷蔵倉庫業は、温度を管理する必要がある物品を保管する倉庫を運営する事業です。
おもに食品(生鮮食品や冷凍食品)、医薬品、化学薬品などを対象とし、低温環境(冷蔵:約0~10℃、冷凍:-18℃以下)で鮮度や品質を維持します。冷蔵倉庫業では、最新の冷却技術や省エネ設備を取り入れており、食品物流や医療業界に欠かせない存在です。
・水面倉庫業
水面倉庫業は、水面を利用して物品を保管する倉庫事業で、とくに原木を水面上で保管する「水面貯木庫」が代表例です。水面で木材を保管することで、乾燥を防ぎ、品質を維持できます。港湾周辺や水域を活用して運営され、木材産業や水運を中心とした物流で重要な役割を果たしています。
営業倉庫の種類

営業倉庫は目的や保管物品の種類に応じて、いくつかの種類に分けられます。また、保管中の物品の品質を保たなければいけないので、保管商品に合わせた条件を満たす営業倉庫が必要です。
ここでは、営業倉庫の種類について詳しく見ていきましょう。
一類倉庫
一類倉庫は最も基準が厳しい倉庫で、防火性能や防犯設備・鼠害防止設備など、さまざまな設備が必須です。設備が充実しており安全性が高いことから、冷蔵が必要なものや危険物を除き、一般雑貨や米などさまざまな物品を保管できる倉庫です。
二類倉庫
二類倉庫は、防火・耐火性能が不要な倉庫になります。さまざまな物品を保管できる一類倉庫と比べ、燃えやすい製品は保管できません。おもに、麦やでん粉そのほか飼料や野菜類などを保管できます。
三類倉庫
三類倉庫は、防水、防火、遮熱、防湿性能のほか鼠害防止性能が不要な倉庫です。このことから、燃えやすいものや湿気に弱い製品は保管できず、保管できるのは陶磁器やガラス器などです。
野積倉庫
野積倉庫は柵や塀で囲まれた土地を使う保管場所になります。防護されたエリアには、消火設備や防犯のための照明を設置する必要があります。建物ではないため、雨風にさらされてもいい、鉱物や土石、原木などを保管できる倉庫です。
水面倉庫
水面倉庫とは、海や水辺に設置されている倉庫です。倉庫という名前ではありますが、屋根や壁がなく、雨風にさらされている施設になっています。おもに原木を保管しており、乾燥を防ぐため水面上で管理されています。
貯蔵槽倉庫
貯蔵槽倉庫は主にサイロやタンクと呼ばれる倉庫になります。袋に入れていないバラの状態の穀物や液体の製品を保管できる施設です。
危険品倉庫
危険品倉庫は、石油、化学薬品などの危険物を保管する倉庫です。危険物を取り扱うので、防火設備も必要になるほか、保管する危険物の種類に合わせた法律の条件(消防法や高圧ガス保安法など)をクリアする必要があります。
冷蔵倉庫
冷蔵倉庫は、水産加工品、食肉、冷凍食品などを常時10℃以下で保管できる倉庫です。倉庫を建てるには、事故の防止や作業員の安全確保のための通報機などの設置が必要になります。
トランクルーム
トランクルームは、美術骨董品や事務文書、家財など個人のものを保管する倉庫です。トランクルームの中でも、国土交通省により認められた倉庫は「認定トランクルーム」とされています。
倉庫業の主な役割(業務)

倉庫業とは、営業倉庫を運営し、第三者から預かった物品を有料で保管する事業です。倉庫業法に基づき、登録を行った事業者のみが運営できます。また、保管中の物品の品質や数量を適切に維持する必要があるため、保管商品に合わせた条件を満たす営業倉庫を登録しなければなりません。
倉庫業の役割は単なる商品の保管にとどまらず、在庫管理、流通加工、ピッキング、など入庫から出荷までの一連の流れを担っています。
具体的な仕事内容を見てみましょう。
・検査、検品
契約先から物品が仕入れされたら、物品の種類や数量に間違いが無いか、不良品が無いかなどの品質を確認します。食品であれば、異臭はないかといった点や、衣類であれば、シミや破損がないかという点をチェックします。
・入庫、保管
確認できた物品を倉庫の中に保管します。この時に物品に管理のためラベリングをし、在庫管理もします。保管するときには、物品の種類に合わせて温度、湿度など適した環境を用意します。
・流通加工
物品の注文が入り出荷の指示かでたら、物品の出荷準備をします。物品の梱包、仕分け、ラベル貼りなどをおこないます。
・ピッキング・配送準備
顧客の指示に基づき、出荷する物品を保管場所から取り出し、配送先別に分別します。
・出荷
配送準備が整った物品を配送トラックに積み込んで出荷します。
倉庫業のこれらの業務を担っていることにより、物流効率の向上や企業の業務負担軽減ができているといえるでしょう。
倉庫業で利用できる倉庫は?

倉庫にもさまざまな種類があるので、どのような倉庫が向いているのか悩む方もいるのではないでしょうか。そもそも、営業倉庫は保管物品によって建築基準が決まっているので、倉庫業を営むためには、建築基準に合った倉庫を建設しなければなりません。
ここでは、倉庫業で利用する営業倉庫の種類として、「鉄骨倉庫」「プレハブ倉庫」「木造倉庫」の3種類について詳しく見ていきましょう。
・鉄骨倉庫
鉄骨倉庫は、おもに鋼材を使用した構造で、高い耐久性や耐震性を備えています。また、建築資材が鋼材なこともあり安定した品質で建てられ、柱や壁を少なくできるので大型の設備や広いスペースを確保しやすいでしょう。
一方で、建設コストがほかの建築方法と比べやや高くなる点や、防さび加工・断熱性の工夫が必要な場合がある点には注意が必要です。
・プレハブ倉庫
プレハブ倉庫は、工場で生産された部材を建築現場で組み立てる建築方式の倉庫です。短期間で建設が可能で、コストも比較的抑えられるため、臨時的な保管場所や中小規模の倉庫として利用されることが多いです。また、建築後に移設や施設の拡張がしやすい点もプレハブ倉庫の特徴です。
ただし、構造の簡易さから耐久性や断熱性が鉄骨倉庫などに比べて劣る場合がある点、規格品であることから建物の大きさや、見た目に自由度がないという点に注意が必要です。
・木造倉庫
木造倉庫は、木材を主体とした構造で、自然素材ならではの温かみが特徴です。木造建築は木材の柔軟性により、耐震性が高く、倉庫から農業関係などさまざまな場面で活用されています。
木造倉庫は建築工期が短く、建築コストが比較的安い点が大きな利点です。なかでも、HC.Home’sの木造倉庫では一般的な建築倉庫の2分の1以下の金額(1坪あたり25万円)から建設可能です。
また、木造倉庫は法定耐用年数が鉄骨倉庫より短いですが、短期間で減価償却年数できるという面では節税を目指せるといったメリットもあり、昨今は木造倉庫を選択するといったケースも増えてきています。
そのほか、木造倉庫は、デザイン性も高く、目的に応じて柔軟に設計できるので、ほかの種類と合わせて木造倉庫の利用検討をおすすめします。
倉庫業を営むときに知っておかなければならない倉庫業法
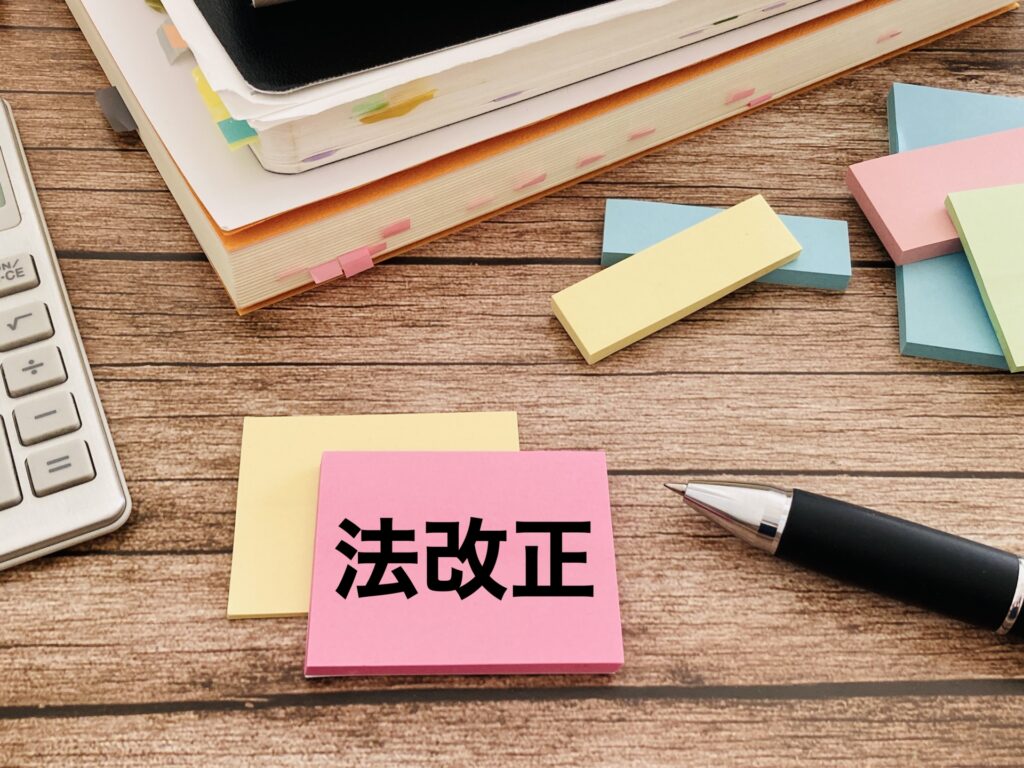
倉庫業を営むためには、倉庫業法の規制に従う必要があります。食品や工業用品、雑貨商品など倉庫業で取り扱う物品はさまざまです。保管の際のトラブルを防ぐため、それぞれの品質を保ちながら管理できるガイドラインが決まっています。
倉庫の登録要件や運営基準、保管中の貨物に関する責任などが定められており、営業倉庫の登録には保管する貨物の種類に合わせて施設基準を満たす必要があります。なかでも、安全性や衛生管理に関する基準に注意する必要があります。
また、保管している貨物の責任は倉庫業者側にあります。倉庫業法では、保管中の貨物に損害が発生した場合の責任についても規定されているため、適切な保険の加入や管理体制の整備が重要になるでしょう。
貨物を預ける企業も、保管する倉庫業側もお互いに不利益を被らないために、倉庫業法の遵守は大切なポイントになっています。
まとめ|倉庫建築ならHC Home’sにお任せください!
いかがでしたでしょうか。
今回は、倉庫業を営むための営業倉庫について種類の解説や自家用倉庫との違い、倉庫業についての解説などをしました。くわえて、倉庫業で利用できる倉庫として、鉄骨倉庫、プレハブ倉庫、木造倉庫の3種類を紹介しています。
なかでも、木造倉庫は、コストパフォーマンスも優れており、デザイン性も高く柔軟に設計できるので、営業倉庫にもおすすめです。
愛知県で営業倉庫の建設を検討されている方は、ぜひHC.Homesにご相談ください。